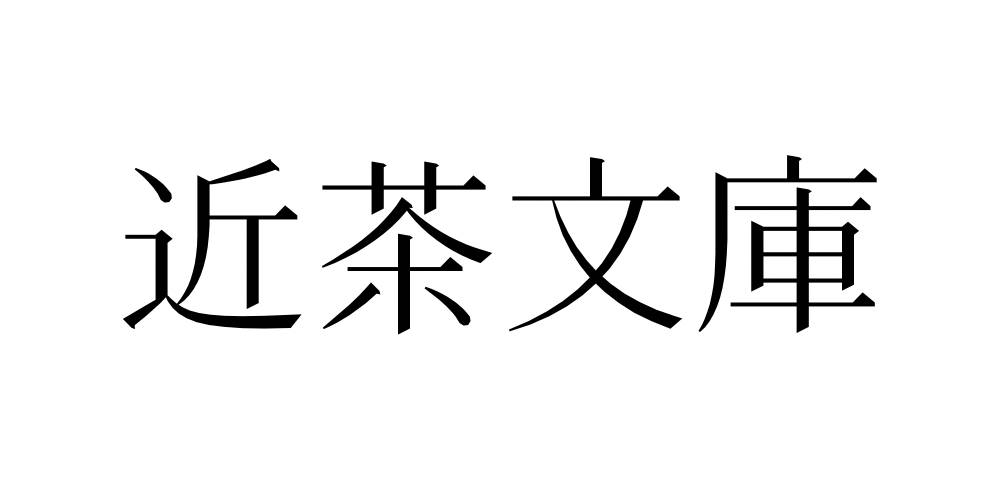私が小さい頃、夏休みのたびに日本中の様々な場所を訪れました。両親の食材をめぐる旅に、私たちも連れて行ってもらったのです。
小豆島に初めて行ったのも、その旅の時でした。
小豆島は面積的には日本で一番小さい島で、周囲200キロほどではありますが、醤油、オリーブオイル、そうめん、ごま油、と実に様々な産業が育っています。 また瀬戸内の海に面しているので魚がたくさんとれる場所でもあります。
今回はそうめんを中心に小豆島の食の話をしたいと思います。
小豆島のそうめん
私は大学を卒業後、小豆島の醤油会社で半年以上働きました。その間に小豆島の食を学びたいという思いから、島のオリーブ畑やそうめん屋で勉強させてもらった経験があります。
小豆島で有名なのが、「島の光」というブランドのそうめんです。小豆島のそうめんの特徴は手延べそうめんであることです。手延べと機械式は作り方に違いがあるため、食感やのどごししが違います。手延べそうめんは、最初に500円玉の直径ほどの太さのそうめんを作り、その周りに油をつけて寝かせてから、太さを小指ほどまでにして、さらに箸2本に八の字になるように巻いたものを、箸を左右に開くことによって伸ばして細くしていきます。
機械式は、手延べのように伸ばすのではなく、太いものをよじって徐々に細くしていくやり方です。機械式では断面が丸い形になるのですが、手延べそうめんでは断面の形がいびつで、丸だけでなく、三角形や四角形の断面が生まれます。また、太さもそれぞれ少しずつ違ってきます。手延べそうめんはこのように、麺がいびつな形をしていることから、のどごしが生まれるのです。
そうめん作りの1日
そうめん屋さんの朝はとても早いです。太陽が最も高くなる正午前後がそうめんを干すタイミングなので、その時間に向けて、作業を始めるのは朝の3時〜4時です。練り始めて、寝かせたり、形を作っていくうちに10〜11時になり、それから天日干しを始めます。雨が降ってしまったら干すことはできないので、晴れの日を探しながら作業をします。
そうめんは作ってから1年〜2年ほど寝かせると美味しいと聞いたことありますか。私も以前はそう思っていました。しかし、私のそうめんのお師匠から、できたてのそうめんを食べさせてもらいました。コシとモチモチ感があり、今まで食べたそうめんと全く違っていたのを覚えています。できたてのそうめんも美味しいのだと教わりました。

そうめんつゆには伊吹島の煮干しがいい
そうめんを食べるためのつゆには、同じく香川県の伊吹島の煮干しがおすすめです。
瀬戸内にある観音寺の沖に伊吹島があります。伊吹島は煮干しで有名です。煮干しにするためには、マイワシではなく、カタクチイワシを使います。同じカタクチイワシでも白っぽいものと黒っぽいものがあり、黒いものは、黒口、そして白いものは白口といって、取れる場所などによって変わります。伊吹島では白口が多く獲れ、品質が良いため、いいだしがとれます。
いい煮干しを選ぶ方法
煮干しの品質は形で見ることができます。煮干はまっすぐではなく、少し曲がっているものが多いですね。いい煮干しを選ぶためには、この曲がり方を見ます。よく見てみると、お腹の方に曲がっているか、背中に曲がってるかの違いがあります。鮮度の良い状態のイワシを干すと、多くはお腹の方に曲がります。
ですので、買うときには腹側に曲がっている煮干しが多いものを選ぶといいでしょう。煮干しのだしは昆布と鰹節でひくだしとはまた少し違った、コクのあるだしが出ます。味をしっかりめにつけたい味噌汁や、そうめんつゆ、うどんつゆなどに適しています。
そうめん作りの最盛期は冬ですが、小豆島では一年を通してそうめん作りを体験させてもらえるところもあります。ぜひ、小豆島を訪れた際にそうめんを干している風景に出会えるといいですね。