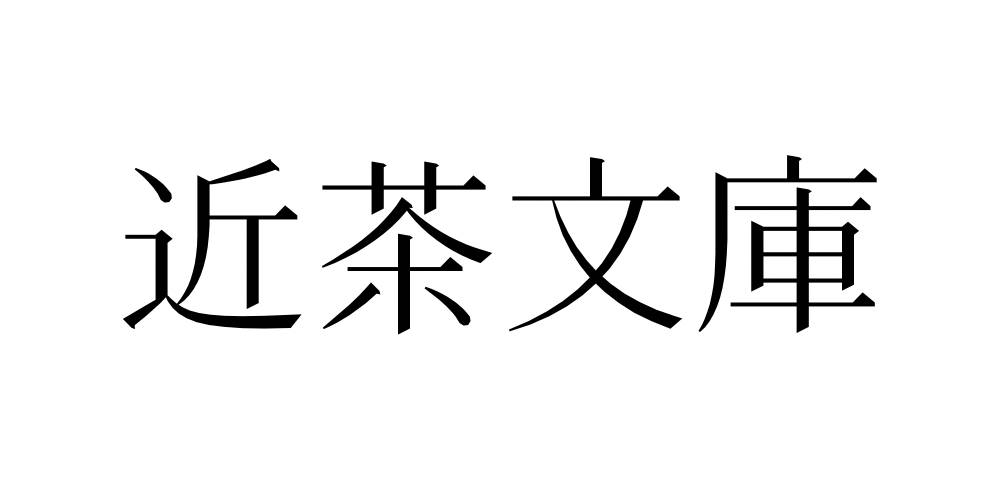7月7日は七夕です。
七夕は「七夕(しちせき)の節供」とも言い、五節供の中のひとつです。
関東では新暦の7月7日に行なっていますが、仙台の七夕祭りなどは今でも月遅れ8月7日前後に行われています。
3月3日の「上巳の節供」、5月5日の「端午の節供」7月7日の「七夕の節供」、9月9日の「重陽の節供」、そして年が明けた1月7日の「人日の節供」が五節供です。
今回は、七夕の由来や、この日にちなんで作る七夕素麺についてのお話です。
七夕の由来
多くの年中行事は中国から伝えられたものが原型となっていることが多く、七夕もその例外ではありません。
七夕の節供は、牽牛星と織女星が1年に1度の逢瀬を楽しむという中国の伝説と、女性が裁縫が上達するようにと祈る「乞巧奠(きこうでん)」という行事が日本に伝わり、初めは主に宮中で行われる年中行事でした。
日本の「棚機津女」の信仰などとも合わさり、この日にケを祓う意味合いのある儀礼や、農耕にまつわる儀礼が行われていたところが各地にあります。
平安時代に宮中で行われていた「乞巧奠」という行事では、時代によって、その形式の変遷はあったようですが、祭壇を設えた上に、琵琶や琴などの楽器、五色の糸と布、旬の食材、秋草などを供えていたようです。
江戸時代になって、今のような、竹の葉に願いを書き入れた五色の短冊を飾る慣習が一般的に行われるようになりました。お供えの糸や布、そして願いを書く短冊は、五色のものを用いますが、この五色は、青(緑)、赤、黄、白、黒であり、それぞれ、木、火、土、金、水を表しています。中国から伝わった陰陽五行の考えです。
七夕の料理
七夕にちなんでつくる料理が「七夕素麺」です。
天の川の流れ、または織姫の系に見立てて、素麺を流れるように置きます。そこへ五色の具を飾ります。きゅうりの緑、カニ身の赤、薄焼き玉子を細く切った錦糸玉子の黄色、軽く焼いたささみの白、海苔または焼いた椎茸の黒です。
この料理は、七夕飾り、すなわち五色の糸や布を表しているだけでなく、素麺を七夕に使うという点で理にかなっています。ちょうど7月から8月の頃は貯蓄していた前年の米が少なくなる季節です。そして、6月の頃は、「麦秋」と言われ、麦の収穫の季節です。麦の収穫は6月初旬に行われます。麦を収穫して、その粉をひいて作ったのが素麺です。
平安時代は、素麺の原型といわれる「索餅(さくべい)」という揚げた唐菓子を作り、小麦の収穫の感謝を表すために神々に備える風習もありました。室町時代の乞巧奠では、索餅を梶の葉で包み、これを素麺で十文字にくくって屋根の上に放り上げたりもしていたようです。
素麺
素麺は麺の中で最も細い麺です。その次に冷麦、そしてうどんという順番で太くなります。
私は手延べそうめんを作る体験を、小豆島で1週間ほど勉強したことがあります。手延べ素麺の良いところは、形が画一化されていないことです。素麺の断面を見てみると、四角形に近いものや、三角形に近いものなど、さまざまな形をしています。このようにさまざまな形をしていることによって、独特な喉ごしが生まれるわけです。
この喉ごしを楽しむためには、なんといっても、茹で上がった麺のコシが大切です。伸びた素麺は美味しくないですよね。コシを出すためには茹で方とすぐに冷ますことが重要です。
素麺の茹で方
沸いた熱湯に素麺を入れます。麺を入れたあとに湯が沸騰してくるとヌメりによって湯が吹きこぼれてしまうので、差し水を用意しておきます。差し水を1カップ(200CC)ほど用意しておいて、沸騰してきたらその半分の100CCほど入れて湯を落ち着かせます。そしてまた再び沸騰したら、残りの100CCを加えて落ち着かせます。そして3回目の沸騰がきたときに、麺を取り出します。
茹で方はもちろん重要ですが、同じように大切なのが冷水で締めることです。一気に締めるために、できる限り流水や氷水で一気にバシャバシャと洗います。これによって余分なヌメりが落ちて、麺がギュッと締まることによって、コシが出てきます。
基本的に小麦粉を使っている麺ものは、一度ゆでた後に冷水で締めることによってコシが出るので、蕎麦やうどんも茹でた後に一度締めてから使うことが多いです。水で冷たくして締めて、それからまた温めて汁の中に入れたり、かけ蕎麦にすると、コシのある麺を楽しむことができます。中には釜揚げうどんのように、冷水で締めずに出す場合もあります。
五色の具を飾った七夕素麺、ぜひ楽しんでください。