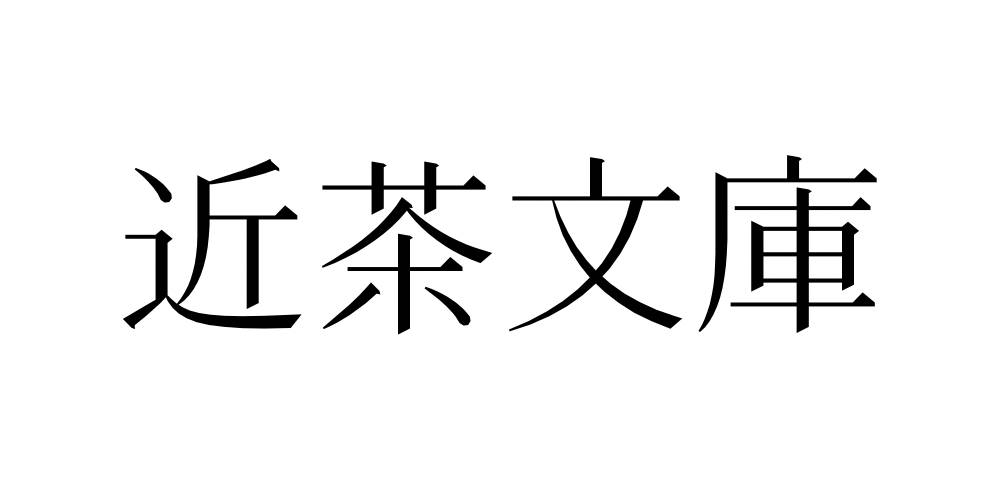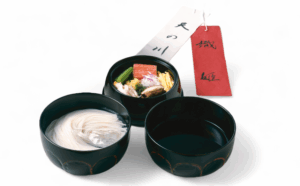日本料理のだしは、とても簡単で色々な料理に使える優れものだということを前回の「だしの基本」の記事で紹介しました。
さあ、実際にだしをひいてみましょう。
今回は最も基本的な、昆布と鰹節のだしです。これを覚えたら、お吸い物、味噌汁、煮物など美味しい料理が作ることができますよ。

用意するもの
- 昆布
- 鰹節
- 鍋
- ざる
- 布巾もしくはキッチンペーパー
- ボウル
- 箸
良い昆布と鰹節の選び方については、前回の記事「簡単に美味しい和食を作るために:だしの基本」を参考にしてください。
昆布は水から
昆布は、鍋に入る長さのものひとつあれば十分です。18センチの鍋であれば、その直径に収まる16センチほどの長さが必要です。
昆布は日高昆布のようにねじれているものであれば、最初にさっと洗って表面のほこりを落とします。表面についている白い粉(マンニット)はうま味成分なので、落とす必要はありません。利尻昆布や真昆布などの平たい昆布であれば、表面は軽く拭く程度で良いです。
まず鍋の中に、必要なだしの量に1カップ分余計に足した量の水を入れておきます。たとえば、5カップのだしが必要であれば、5カップ+1カップで6カップの水です。
そこへ昆布を入れます。
昆布はゆっくりと温度を上げる
水の中に昆布を入れたら、火をつけましょう。中火くらいで、ゆっくり温度を上げていきます。
昆布は冷たい温度の水からでも、うま味が出ます。火にかける前に水に入れ、ゆっくりと温度を上げます。急に高い温度の中に入れると、昆布からヌメりや色や匂いが出てきてしまいます。ゆっくりと温度を上げましょう。
昆布を入れた鍋に火を入れて温度が上がってくると、昆布がゆらゆらと動き出します。そして、昆布の周りに小さい気泡ができます。昆布も広がってきます。日高昆布はねじれているので、最初は細かったものが、倍近くに広がります。このように、小さい気泡が出てきて、昆布が動いてきて、日高昆布の場合は幅が広がったら、だいたい70度くらいに温度が上がっている目安です。こうなったら昆布は取り出しましょう。
この昆布にはまだうまみが残っているので、これは冷凍庫などに取っておき、集まったら醤油とみりん、砂糖で佃煮などを作ることができます。
鰹節を入れる
昆布を取り出したら、火を強くしてください。今までゆっくり温度を上げてきましたので、だしには少し昆布の色がついて、香りもいいです。
温度を上げて沸騰したら、鰹節を入れましょう。鰹節の量は、鍋の表面を全体的に覆うくらいあればいいでしょう。鰹節を入れたら、一度火を消します。量の目安としては1カップ取るのに3gから4gほどです。
鰹節を入れてから火を消すと、水面から飛び出ている鰹節は静かに沈めます。この時、箸でかき回したりしてしまうと、鰹節から酸味が出て、酸っぱいダシになります。飛び出ている鰹節が静かに沈むように、少し箸で押さえる程度にしてください。鰹節を軽く沈めたら1分ほど待ちます。
1分待つ間に濾す準備をしましょう。料理教室では、さらしを使って濾しますが、なければキッチンペーパでもいいです。さらしをボウルの上に置いたざるの上に置いておきます。この上に鍋の中をあけます。最後に、さらしの四隅を合わせてから箸で押さえて一度きりッと絞ればいいです。この鰹節も取っておいて、後でふりかけなどを作ったりしてもいいです。

だしを「ひく」
私たちは、だしをつくることを「だしをひく」と言います。なぜ「ひく」という表現をするかというと、昆布や鰹節の、美味しい部分だけを引き出すからです。確かに、うま味をすべて出したければ、昆布も鰹節も全て最初から入れてぐつぐつ煮てしまえば、うまみは出ますが、ヌメりや色のついたダシになり、味を損ねてしまいます。
鰹節は高温になってから入れます。鰹節を昆布と同じタイミングで入れないのは、鰹節は魚なので、低い温度で入れてしまうと生臭みが出るからです。ここを気をつけると、美味しいだしがひけるでしょう。
美味しくひけただしの味
薄い琥珀色で、濁りのない、いい香りのだしがひけたはずです。
このだしを飲んでみるとわかると思います。ふくよかで、鰹節の香りと、昆布の味がします。これは味のベースとなるうま味のスープです。ここにひとつまみの塩が入れると、香りと味が大きく変化します。塩とだしのバランスによって旨みがグッと引き立つのです。
だしに食材を入れて、そして調味料を入れて、そして料理が完成していくのです。
だしは保存できる?
だしは少しであれば冷蔵庫で保存できます。
保存方法はガラスのボトルに入れて、冷蔵庫に入れておきます。次の日のお味噌汁に使ったりできますが、1日か2日ほどしか持ちません。香りもなくなっていきますので、なるべく早く使ってください。香り高いお吸い物などには、ひきたてのだしを使った方が美味しいです。
だしは冷凍すると水っぽくなってしまいますので冷凍には向きません。そして、日本料理のだしは水を足してしまうと、水っぽくなるので、使う量に少し足りないからといって水を足すのではなく、最初から自分の必要な量を考えて、だしを用意してください。
美味しい料理は美味しいだしから始まります。
ぜひ、皆さんもだしをひいてみてください。