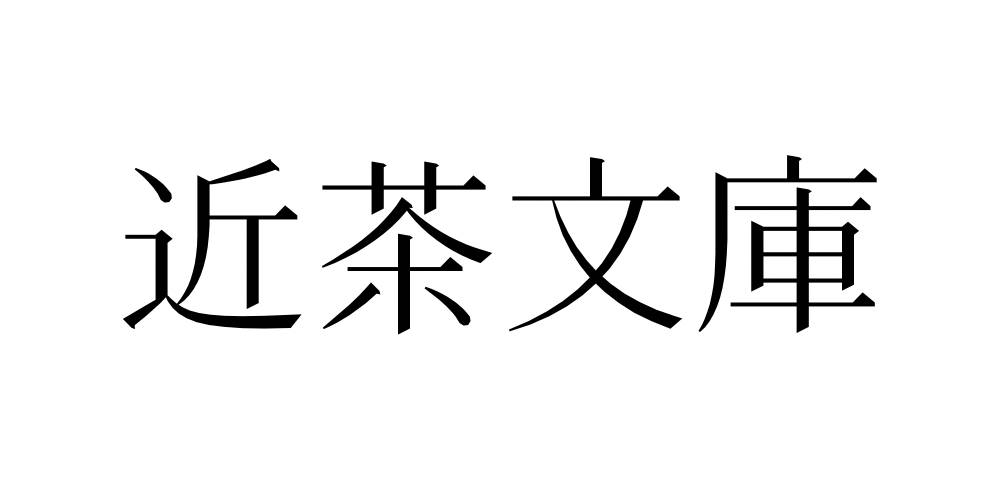日本料理手帖– category –
-

けしょうじお【化粧塩】
化粧塩とは、魚を姿焼きにするときに使う手法です。 魚はそのまま焼いてしまうと、ヒレは焼け焦げてしまい、見た目が悪くなります。そこで、ヒレに塩をつけてから焼くことによって、塩でヒレが保護されて焼け焦げず、綺麗な形を保つことができます。また味... -

ひらづくり【平造り】
平造りとは、刺身の切り方の一種です。 鰹やマグロ、鯛などの刺身によく用いられます。大皿料理や大皿に盛り付ける際に、切り身を文字のように整然と並べることで見た目が美しくなります。 魚の柵をまな板の左側に置いて、柵の右端から切り、切り身はまな... -

きあげ【生あげ・気あげ】
茹で方の一つの方法。 野菜などを茹でた後に、水にさらさずにざるなどに取って冷ますことを言う。 緑の野菜などは茹でた後、水にさらして冷ますのが一般的である。水につけて冷ます方法が最も緑の色をきれいに保つことができるが、水にさらした後に食材の... -

しもふり【霜ふり】
肉、魚、野菜などの素材を、さっと熱湯に通し、アクや余分な水分を除き、味のふくみを良くするための下ごしらえ。 歴史的には江戸時代から使われるようになり、それ以前は「湯白める」「湯引き」と呼ばれていた。もとは、ザルにのせた魚にさらしを被せ、そ... -

てりやき【照り焼き】
醤油、砂糖、みりんを合わせたたれをつけ、照りを出した焼きもの。 鶏肉、ぶり、さわらなどに用いる。 照り焼きを上手に作るコツ:最初からタレをつけて焼くと焦げてしまう。まずは食材に塩や醤油で下味をつけて焼き、火が入ってから、仕上げにタレを3〜... -

あんばい【塩梅】
塩梅。味加減のこと。調味のぐあい。程よい味。 古くは、料理は味づけされておらず、自ら食べる時に調味をしていた。その調味は塩と酸味で行なっていたことから、塩梅という字が生まれたと考えられる。
1