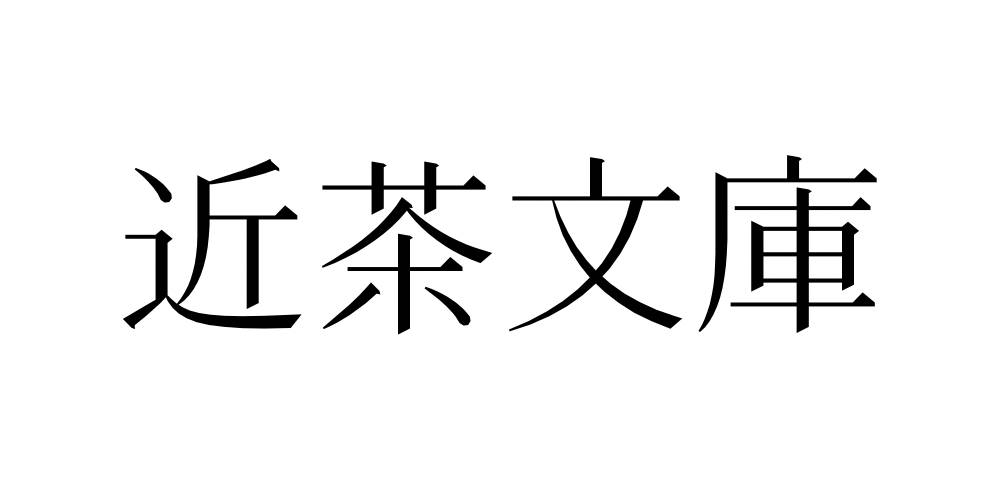柳原尚之– Author –
 柳原尚之
柳原尚之
近茶流宗家 柳原料理教室 主宰
博士(醸造学)
東京・赤坂の柳原料理教室で、日本料理、茶懐石の研究指導にあたっている。
NHK大河ドラマなどのテレビ番組の料理監修、時代考証も数々手がける。 2015年文化庁文化交流使、2018年農林水産省日本食普及の親善大使に任命され、世界へ日本料理を広める活動を行う。
ライフワークは江戸時代の食文化の研究と日本料理・日本文化の継承、そして子ども向けの和食料理本の執筆・講義を通した子どもへの食育。
近茶流 柳原料理教室ホームページ
https://www.yanagihara.co.jp
-

味噌の色ってどうして違う?
日本の台所にとって馴染みの存在である味噌。日々の料理で何気なく使っている醸造調味料です。 でも・・疑問に思うことはありませんか? なぜ、味噌によってこんなに色の違いがあるんだろう? 味噌汁にするとき、使う味噌によって必要な量が違う? 味噌に...和食読みもの -

1月ーふきのとう【蕗の薹】
フキノトウは、山菜の中でもひときわ早く春を告げる存在です。まだ地面の冷たさが残る頃、時には雪を押しのけるように顔を出す姿は、冬から春への移ろいを静かにに伝えてくれます。フキノトウはフキの花茎の部分であり、花が終われば葉が伸び、やがて私た...旬だより -

新しい食育ー子どもたちへ食を伝えるプログラミング的思考
未来の和食はどんなものになっているだろうか。 「和食」「日本料理」と一言にいっても、そのあり方は、時代とともに大きく変化しています。 今の日本料理の味や姿は、100年前とは言わず、10年前のそれとも異なり、変化のスピードも速くなっている、...和食読みもの -

10月ーくり【栗】
小さいころ、栗拾いをしたことを今でも覚えています。 あのときの栗は山栗だったのでしょうか。小さく、いがに包まれ、手で触ると痛いので、靴でいがを広げながら拾ったものです。 大人になってから、丹波の栗山を歩いた際にも収穫を手伝ったことがありま...旬だより -

福沢諭吉 「肉食のススメ」
あなたの好きな牛肉料理は何ですか? 日本人は、すき焼きを思い浮かべる方も多いと思います。 今では日本料理の代表格のひとつであるすき焼きですが、食べ始めたのは明治になってから。 当時は、牛鍋やあぐら鍋と呼ばれていましたが、この料理を推奨したと...和食読みもの -

9月ーまつたけ【松茸】
松茸は日本を代表する秋の味覚であり、独特の香りが特徴です。その香りは日本人には良い香りとして感じられますが、香りの好みは国によって異なるため、外国の方では松茸の香りを好まない人がいると聞きます。 現時点では、松茸はすべて天然です。赤松の根...旬だより -

小豆島のそうめんの話
私が小さい頃、夏休みのたびに日本中の様々な場所を訪れました。両親の食材をめぐる旅に、私たちも連れて行ってもらったのです。 小豆島に初めて行ったのも、その旅の時でした。 小豆島は面積的には日本で一番小さい島で、周囲200キロほどではあります...和食読みもの -

8月ーえだまめ【枝豆】
枝豆は大豆の若いもので、別名「あぜ豆」ともよばれます。 昔は田んぼのあぜ道に多く植えられ、畔の強度を上げる役割を果たしていました。また、豆類であるため、窒素肥料を自ら作り出し、田んぼの栄養素を取る心配がありません。最近は、黒豆など大豆では...旬だより -

七夕を彩る料理「七夕素麺」
7月7日は七夕です。 七夕は「七夕(しちせき)の節供」とも言い、五節供の中のひとつです。 関東では新暦の7月7日に行なっていますが、仙台の七夕祭りなどは今でも月遅れ8月7日前後に行われています。 3月3日の「上巳の節供」、5月5日の「端午の節供」...暦と料理 -

けしょうじお【化粧塩】
化粧塩とは、魚を姿焼きにするときに使う手法です。 魚はそのまま焼いてしまうと、ヒレは焼け焦げてしまい、見た目が悪くなります。そこで、ヒレに塩をつけてから焼くことによって、塩でヒレが保護されて焼け焦げず、綺麗な形を保つことができます。また味...日本料理手帖